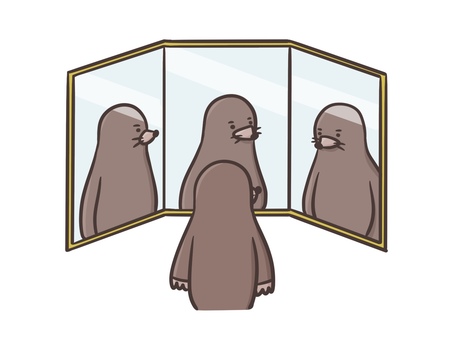導入
サービスを作り込んでいくと、気づけば似たようなフレームをいくつも描いてしまうことがあります。
私自身も「コアフレーム」と呼ぶものを3種類ほどつくり、正直「違いは何?」と混乱していました。
でも整理してみると、とてもシンプルな答えにたどり着きました。
それは 同じプログラムを「根拠」「仕組み」「結果」という3つの角度から説明していただけだったのです。
なぜフレームが増えるのか?
フレームが複数できる理由はシンプルです。
相手によって響くポイントが違うから。
- 理屈で納得したい人には「根拠」
- 再現性を確かめたい人には「仕組み」
- 自分事としてイメージしたい人には「結果」
だから、伝える角度を変えると自然にフレームが増えるのです。
① 心理学的背景(根拠)
「科学的に裏付けられています」と伝えることで、安心感を与えます。
- 選択理論心理学=人の行動はすべて選択である
- コーチング=問いで気づきを引き出す
- NLP心理学=言葉や思考パターンを整えると行動が変わる
これらを土台に、弊社は**「原理原則 × 自己信頼 × 思考のダイエット」**というフレームを体系化しました。
② 実装メカニズム(仕組み)
「どうやって成果に直結するのか」を見せる部分です。
- 取捨選択=やらないことを決め、エネルギーを回復
- ベイビーステップ=15分単位で小さな成功体験
- セッション調整=その場で軌道修正し、最速で成果へ
👉 仕組みを知ると「これなら続けられる」と納得感が高まります。
③ ベネフィット訴求(結果)
最後は「このプログラムを受けるとどうなるか」。
キャッチコピーはシンプルに:
「苦手を削ぎ落とし、習慣を最速で成果へ」
- 苦手に奪われるエネルギーを減らす
- 小さな積み重ねで自信を回復する
- 習慣が成果へ直結する
読者に「自分にもできそう」と未来を描いてもらう部分です。
たとえ話で整理
これはちょうど「家」を説明するのに似ています。
- 根拠=地盤(この家はしっかり建っていますよ)
- 仕組み=間取り(ここにキッチン、ここに寝室)
- 結果=住み心地(ここに住むと快適で幸せですよ)
どれも同じ家ですが、角度を変えて説明しているだけなんです。
実際の使い分け
- セミナー:根拠 → 仕組み → 結果の順で話す
- ホームページ:結果を先に出し、仕組み・根拠を補足
- 法人提案:根拠を先に置き、仕組み・結果で締める
まとめ
フレームが複数できてしまうのは「失敗」ではありません。
むしろ、同じプログラムを「根拠・仕組み・結果」という3つの顔で語れることは強みです。
相手によって入口を変えられる柔軟性があるからこそ、伝わる範囲が広がります。
次に大切なのは「どの場面でどの顔を見せるか」をデザインすること。
👉 フレームが増えたことに迷う必要はありません。
それは、伝える力が広がった証拠なのです。